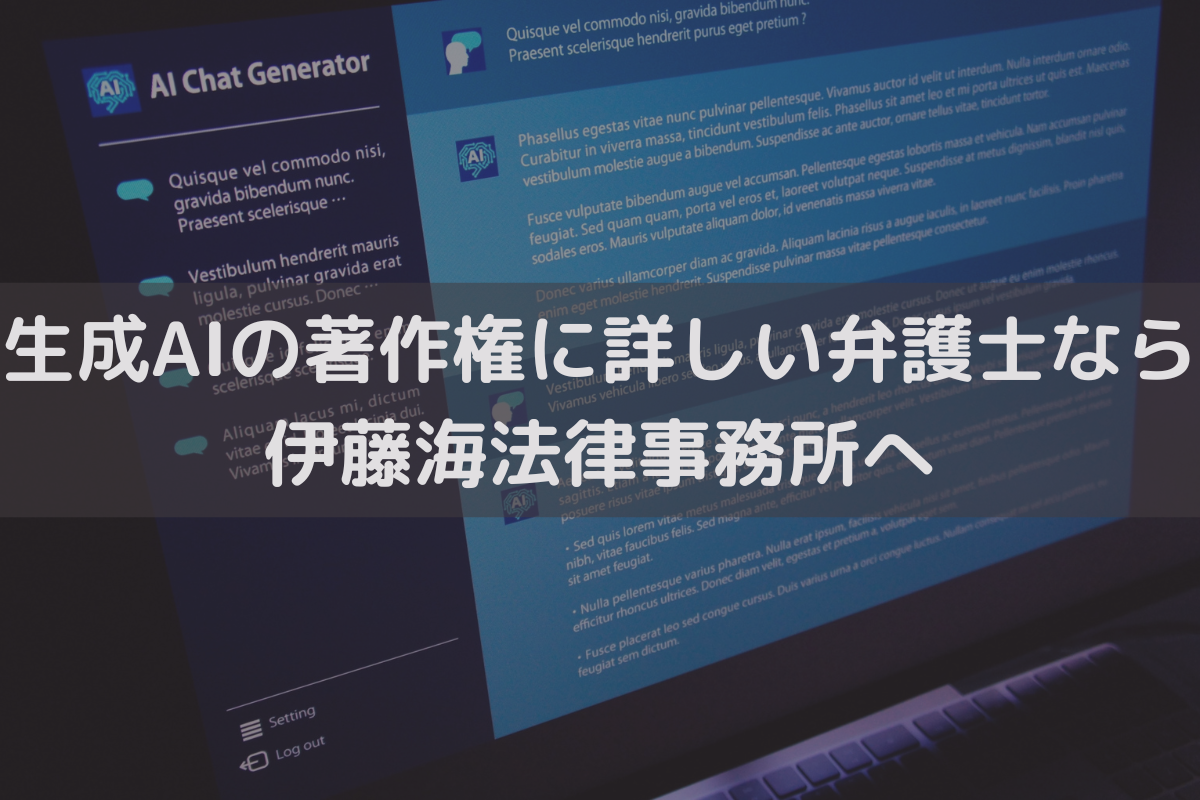生成AIはあっという間に席巻し、今や生成AIによる成果物は世に溢れています。しかし、生成AIを活用する際には著作権侵害に注意しなければなりません。著作権の基本を知らないまま生成AIを活用すれば、他者の著作権を侵害するおそれもあるでしょう。
では、生成AIに他者の著作物を学習用データとして読み込ませることは、著作権侵害にあたるのでしょうか?また、生成AIを使用した創作物は、著作権の保護対象となるのでしょうか?今回は、生成AIと著作権との関係について、弁護士がくわしく解説します。
なお、当事務所(伊藤海法律事務所)はカルチャー・テクノロジー法務に強みを有しており、生成AIと著作権にまつわる相談についても豊富な対応実績を有しています。生成AIと著作権との関係について相談できる弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所までお問い合わせください。
生成AIとは
生成AIとは、事前に学習したデータに基づき、テキストや画像、動画、音楽などを生成する人工知能のことです。
生成AIによる成果物は当初こそぎこちなさが目立ち、人の目で見ればすぐに「生成AIによる成果物だ」と判断できるものばかりでした。しかし、生成AIの精度は飛躍的に向上しており、近年では一見しただけでは人による作品と区別しづらくなっています。
著作権の概要
著作権とは、著作物を保護する権利のことです。著作権は商標権などのように登録することで発生するのではなく、著作物を創作した段階で自動的に発生します。つまり、保護を受けるため、出願などの手続きは必要ありません。
では、著作権の保護対象である著作物とはどのようなものであり、著作権者となるのは誰なのでしょうか?ここでは、著作権の概要について解説します。
著作物とは
著作権の対象となる著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です(著作権法2条1項1号)。
著作物の範囲は非常に広く、出版されている漫画や小説、著名人によるイラストなどだけが保護対象となるわけではありません。著作物の定義に、「著名であること」などの限定はされていないためです。そのため、幼児が描いた絵や一般個人がスマホで撮影した写真、企業のブログ記事なども著作物となり得ます。
また、無償でインターネット上に投稿したからといって著作物性が失われるわけでもありません。個人が制作してSNS上に投稿されたイラストも、引き続き著作権の保護対象です。
著作権者となるのは誰?
著作権の権利者である著作権者となるのは、原則として、その著作物を創作した著作者です。ただし、必ずしも著作者がイコール著作権者であるとは限りません。なぜなら、著作権は譲渡が可能であるためです。
たとえば、著作者Aが創作した著作物aの著作権をB社に譲渡した場合、著作物aの著作権者はB社となります。一方で、著作権が譲渡されても著作者までは変動せず、著作者は引き続きA氏のままです。
著作権者には他にもいくつかの例外があります。著作権者の判断でお悩みの際は、伊藤海法律事務所までご相談ください。
著作権侵害の主な成立要件
著作権を侵害すると、差止請求や損害賠償請求などの法的措置の対象となります。では、著作権侵害の有無はどのような視点から判断されるのでしょうか?ここでは、著作権侵害の成立要件である「類似性」と「依拠性」について、それぞれ概要を解説します。
- 類似性があること
- 依拠性があること
なお、実際のケースにおいて、著作権侵害であるか否かを判断することは容易ではありません。著作権侵害がされてお困りの際や、権利者から著作権侵害を疑われてお困りの際には、伊藤海法律事務所までお早めにご相談ください。
参照元:AIと著作権(文化庁著作権課)
類似性があること
著作権侵害の1つ目の要件は、類似性があることです。類似性とは、問題となっている著作物の創作的表現が、他者の著作物と同一または類似している状態を指します。
ただし、部分的に似通っているだけではなく、著作物の「表現上の本質的な特徴を直接感得できること」が必要とされます。
依拠性があること
著作権侵害の2つ目の要件は、依拠性があることです。依拠性とは、「既存の著作物に接して、それを自己の作品の中に用いること」を指します。非常に平たく言い換えると、「元になった著作物の存在を知ったうえで、これを元に創作した」ということです。
先ほど解説したように、著作権を発生させるために登録などを受ける必要はありません。裏を返せば、世に存在する著作権を網羅的に調べることは不可能だということです。そのため、登録制を採っている商標権などとは異なり、著作権は偶然の一致である場合(つまり、依拠性がない場合)には侵害が成立しません。
他人の著作物を生成AIに学習させてアウトプットさせることは著作権侵害に当たる?
生成AIは、インターネット上に無数に存在する著作物を学習し、アウトプットの精度を高めます。自身で生成したデータのみを学習させていては生成AIの精度を高めることは困難であり、無数のデータから学習できることこそが生成AIの生成AIたる所以であるともいえるでしょう。
そのため、生成AIは他人の著作物を学習していることがほとんどです。むしろ、他人の著作権を一切取り込んでいない生成AIは、存在しないとさえいえるでしょう。では、他人の著作物を生成AIに学習させてアウトプットさせることは、著作権侵害にあたるのでしょうか?
これは、一概に判断できるものではありません。個別の案件ごとに、類似性や依拠性の有無から著作権侵害の有無を判断することとなります。ただし、そもそも生成AIによる著作権侵害が疑われている段階で、相当程度の類似性はあることが前提でしょう。そこで特に問題となるのが、依拠性の有無です。
たとえば、問題となっている生成AIの成果物Xが著作者Aによる著作物aと類似していても、生成AIの使用者がその著作物Aの存在を知らなかったと判断されれば、依拠性がなく著作権侵害は成立しないこととなります。とはいえ、その著作物aが、日本に住んでいれば知らないと言い逃れることが難しいほどに著名である場合には、「知らない」との主張自体に疑義が持たれる可能性はあるでしょう。
一方で、生成AIの利用者が著作者Aの作風に似せるために著作者Aの作品ばかりを意識的に生成AIに読み込ませ、その結果成果物Xがアウトプットされたのであれば、著作権侵害と判断される可能性が高くなります。
このように、生成AIに著作物を学習用データとして読み込ませることが著作権侵害にあたるか否かは、ケースバイケースです。一概に判断できるものではないため、お困りの際は伊藤海法律事務所までご相談ください。
生成AIがアウトプットした成果物は著作権の保護対象となる?
生成AIと著作権にまつわるもう1つの視点として、生成AIがアウトプットした成果物が著作権の保護対象となるか否かという点があります。
生成AIによる成果物が著作権の保護対象となるのであれば、その成果物を他者が自由に模倣することはできません。一方で、著作権の保護対象とならないのであれば、原則として誰でも自由に利用できることとなります。
結論としては、生成AIによる成果物に著作権が発生するか否かは、ケースバイケースです。
前提として、著作権の保護対象となる著作物は「思想または感情を創作的に表現したもの」と定義されており、人間による創作であることが必要です。ゾウが鼻を使って器用に絵画を描いたとしても、「思想または感情を創作的に表現したもの」ではないため、著作権の保護対象とはなりません。
同様に、生成AIが「自ら」作り出したものであれば、これは著作権の及ぶ著作物ではないこととなります。生成AIは人間ではないため、「思想または感情を創作的に表現したもの」とはいえないためです。つまり、いくら精巧かつ独創的(に見える)成果物であったとしても、生成AI自身が著作者となることはありません。
一方で、生成AIを「道具」として使った人が、成果物の著作者となる余地はあります。たとえば、「何か適当に絵を描いて」という程度の簡単な指示を生成AIに与え、その結果出力された成果物は、著作物とはいえないでしょう。ここには、人間の思想または感情が反映されているとは言い難いためです。
その反面、人がプロンプトを相当程度工夫した結果、生成AIが出力した成果物は、著作権の保護対象となり得ます。なぜなら、人間の思想または感情が創作的に表現されていると考えられるためです。
なお、この場合においても生成AIが著作権者となるわけではありません。著作権者となり得るのは、生成AIを活用した人間です。生成AIは絵の具やパソコン、illustrator等のソフトなどと同じく、人間の創作活動のための「道具」として捉えられます。
このように、生成AIによる成果物が著作物となり得るか否かも、ケースバイケースです。生成AIによって出力された成果物の保護をご検討の際は、伊藤海法律事務所までご相談ください。
生成AIで著作権侵害をされた場合の対応
生成AIによって著作権侵害がされている可能性があると考える場合、どのように対応すればよいのでしょうか?ここでは、インターネット上に投稿された生成AIによるイラストが著作権侵害にあたると考える場合における、一般的な対応の流れについて解説します。
- 弁護士へ相談をして著作権侵害であるか否かの見通しを立てる
- 差止請求をする
- 損害賠償請求をする
弁護士へ相談をして著作権侵害であるか否かの見通しを立てる
生成AIによる著作権侵害の有無を、自身で判断することは容易ではありません。そのため、まずは生成AIや著作権にくわしい弁護士へ相談すべきでしょう。弁護士へ相談することでそのイラストが侵害行為に当たりそうか否かの見通しが立てられ、その後の具体的な対応が検討できます。
生成AIで著作権侵害がされてお困りの際は、伊藤海法律事務所までご相談ください。
差止請求をする
弁護士へ相談したうえで、そのイラストが著作権侵害にあたる可能性が高いと判断した場合には、相手方に差止請求を行います。
差止請求とは、該当のイラストが自身の著作権を侵害している可能性が高いことを指摘したうえで、そのイラストの使用をやめるよう求めるものです。仮に、著作権侵害にあたるそのイラストがグッズ化されるなどして頒布されているのであれば、その販売や製造を辞めるよう求めることもできます。
なお、インターネット上に投稿されたイラストである場合、投稿者が匿名であり身元がわからない場合もあるでしょう。その場合には、差止請求に先立って投稿者の身元の特定が必要となる場合もあります。投稿者が匿名であっても、発信者情報開示請求などの手段によって投稿者を特定する道はあるため、諦める必要はありません。
損害賠償請求をする
生成AIによる著作権侵害によって損害が生じた場合には、相手方への損害賠償請求が検討できます。損害賠償請求とは、相手の不法行為(著作権侵害)によって生じた損害を償えるだけの金銭の支払いを、相手方に対して求めるものです。
損害賠償請求はまず、弁護士から相手方に内容証明郵便を送るなどして行うことが多いでしょう。この段階で相手が請求に応じれば、事案は解決となります。一方で、相手が任意に賠償金を支払わない場合には、裁判上での請求へと移行します。
生成AIでの著作権侵害について弁護士へ相談する主なメリット
生成AIの著作権侵害について弁護士へ相談することには、どのようなメリットがあるのでしょうか?ここでは、弁護士へ相談する主なメリットを2つ解説します。
- 知らずに著作権侵害をする事態を避けられる
- 著作権が侵害された際・侵害が疑われた際に的確な法的措置が可能となる
伊藤海法律事務所は生成AIに関するリーガルサポート実績を豊富に有しています。生成AIの著作権侵害について相談できる弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
知らずに著作権侵害をする事態を避けられる
生成AIの著作権について弁護士へ相談することで、自身が知らずに著作権侵害をする事態を避けることが可能となります。
著作権侵害は、「法律をよく理解していなかった」からといって免責されるものではありません。また、裁判となった結果最終的に侵害行為ではないと判断されたとしても、裁判には長い時間と費用、労力などがかかるため、侵害を疑われて裁判に至ること事態が不利益でしょう。
生成AIの活用について日ごろから弁護士に相談しておくことで、著作権侵害や著作権侵害を疑われる事態を回避しやすくなります。
著作権が侵害された際・侵害が疑われた際に的確な法的措置が可能となる
インターネット上などで自身や自社の著作権侵害が疑われるイラストや画像などを見つけた際、どのように対応すべきか判断に迷うことも多いでしょう。そのような際、著作権侵害の有無が明確でない段階でそのイラストなどの投稿者などに直接連絡を取ったりSNS上で「リプライ(投稿へのコメント)」をしたりすれば、トラブルが複雑化したり対応が困難となったりするおそれが生じます。
著作権侵害と思われる事象が生じた際に早期に弁護士へ相談することで、状況に応じた的確な対応が可能となります。
また、生成AIの活用にあたって自身には意図的に模倣した意識がないにもかかわらず、権利者を名乗る者から差止請求などがなされる場合もあるでしょう。そのような際にも、早期に弁護士へ相談することで、的確な対応をとることが可能となります。
お困りの際は、伊藤海法律事務所までお早めにご相談ください。
生成AIの著作権について相談できる弁護士なら伊藤海法律事務所へお問い合わせください
生成AIの著作権について相談できる弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所までご相談ください。最後に、当事務所の主な特長を4つ紹介します。
- カルチャー・テクノロジー法務に強い
- 代表は弁護士のほか弁理士資格も有している
- 連絡手段が多様である
- 英文の契約書にも対応している
カルチャー・テクノロジー法務に強い
伊藤海法律事務所は、カルチャー・テクノロジー法務に強みを有しており、多くのIT企業やシステム開発会社に顧問として参画しています。また、ポップカルチャーやトップカルチャー、サブカルチャービジネスに関わる企業・個人の支援にも力を入れています。
これらの業界では生成AIが非常にホットな話題であり、生成AIの著作権に関連するご相談を受けることも少なくありません。このように、当事務所は生成AIの著作権に関して豊富なサポート実績を有しています。
代表は弁護士のほか弁理士資格も有している
伊藤海法律事務所の代表・伊藤海は弁護士であるほか、弁理士資格も有しています。弁理士は、知的財産を専門とする国家資格です。そのため、商標権や著作権などの知的財産の保護についても一貫したサポートの提供が可能です。
連絡手段が多様である
伊藤海法律事務所は顧問契約プランも展開しており、顧問契約をいただいた場合にはLINEやSlack、Chatworkなど多様な手段による連絡が可能となります。そのため、困りごとが生じた際に逐一予約をとって事務所まで足を運ぶ必要はなく、気軽に相談できます。また、法務部のグループチャットに弁護士を追加いただくことも可能です。
英文の契約書にも対応している
カルチャー・テクノロジー業界においては、海外の企業や個人と契約すべき場面も少なくないでしょう。伊藤海法律事務所は英文の契約書にも対応しているため、海外との取引についても一貫したリーガルサポートが可能です。
まとめ
生成AIと著作権侵害について、弁護士が解説しました。
他者の著作物を生成AIへ取り込むことが著作権侵害にあたるか否かは、状況によって異なります。また、生成AI自体が著作権者や著作者になることはない一方で、生成AIによる成果物が、プロンプトを創造した人の著作物となることはあり得ます。
生成AIと著作権の問題には、自身での判断が難しいものも少なくありません。思わぬ侵害行為を避けるため、そして侵害された際のスムーズな対応を実現するため、相談先の弁護士を見つけておくと良いでしょう。
伊藤海法律事務所はカルチャー・テクノロジー法務に強みを有しており、生成AIと著作権に関するリーガルサポートについても豊富な実績を有しています。生成AIや著作権について相談できる弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。