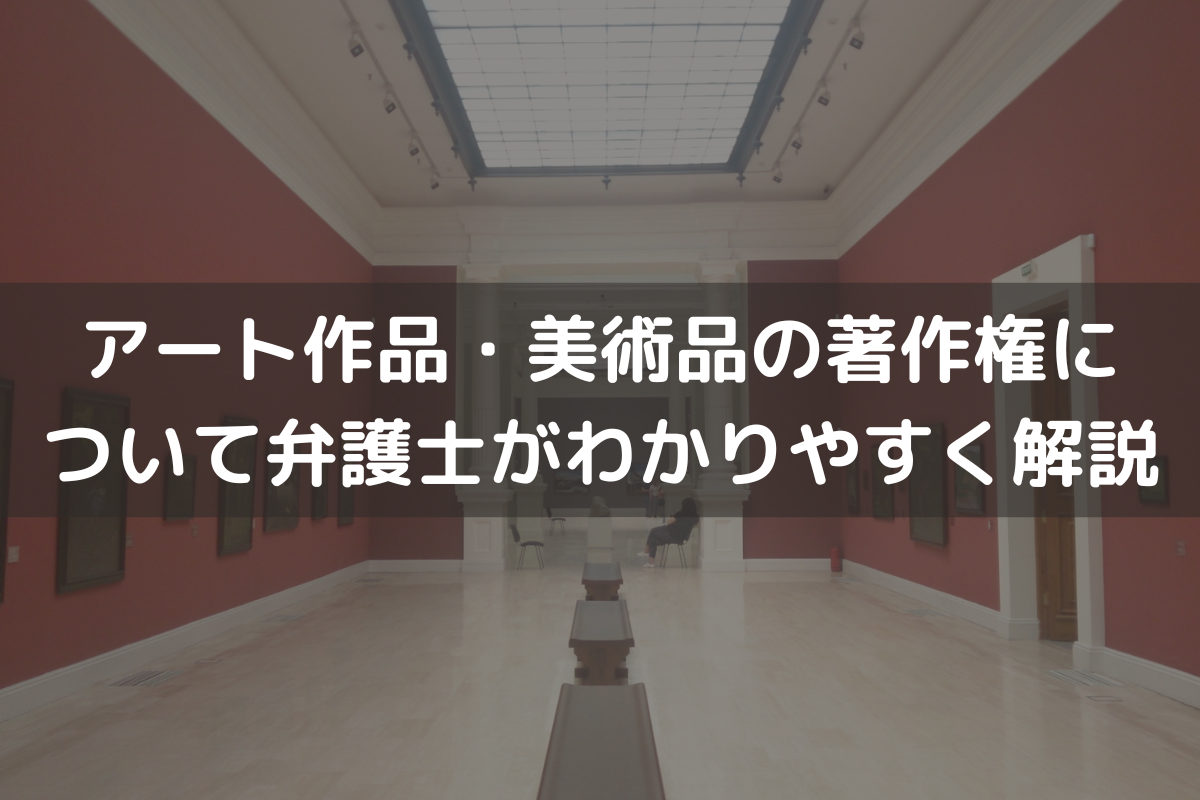写真や絵画などのアート作品には、「著作権」があると聞いたことがあるでしょう。しかし、著作権については誤解が多く、誤解によるトラブルも少なくありません。
では、著作権とはどのような権利なのでしょうか?今回は、アート作品を中心に、著作権について弁護士がくわしく解説します。うっかり著作権侵害をしてしまわないよう、著作権について理解を深めておきましょう。
なお、勤務先の会社の業務の一環で著作物を創作する「職務著作」の場合は、さらに複雑な論点が生じます。そのため、この記事では、特に言及がない限り、職務著作ではない前提で解説します。
著作権の概要
著作権については、誤解が少なくありません。そこで、はじめに著作権の概要を解説します。
著作権とは
著作権とは、「著作物」を保護するための権利です。
著作権は一つの権利ではなく、後ほど解説するとおり、さまざまな権利が束になったものです。そのため、実際に著作権の譲渡などをする際は、著作権のうち「どの権利」を対象とするのかを意識して契約を締結しなければなりません。
著作権の対象となるもの
著作権の対象となるのは「著作物」です。
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」を指します(著作権法2条1項1号)。著作権法では、著作物として次のものが例示されています(同10条1項)。
- 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
- 音楽の著作物
- 舞踊又は無言劇の著作物
- 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
- 建築の著作物
- 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
- 映画の著作物
- 写真の著作物
- プログラムの著作物
ただし、これはあくまでも例示であり、ここに挙げられていないものが著作物でないとは限りません。また、ここに挙がっているものでも、「思想又は感情を創作的に表現したもの」に該当しなければ、著作物に該当しないこととなります。
とはいえ、著作物に該当するハードルは高いものではありません。プロの画家が描いた絵やプロが撮った写真が著作物に該当するのはもちろん、一般個人がスマートフォンで撮影した写真であっても、著作権の対象となり得ます。
また、幼児が描いた絵であっても、著作権の対象となる可能性があります。つまり、プロであることや創作にあたって熟考したことなどは、著作権が発生する要件とはなりません。
また、SNSなどインターネット上に投稿されているからといって著作権が放棄されているわけではないため、注意が必要です。
「著作者」と「著作権者」の違い
著作物の制作者を「著作者」、著作権を有する者を「著作権者」といいます。
創作段階では著作者と著作権者は原則として同一である一方で、著作権の譲渡によって、著作者と著作権者が別の者となることはあり得ます。一方、著作者は著作物を創作した者であることから、著作権が移転しても「著作者」が変わることはありません。
たとえば、画家であるA氏がアート作品を描いた場合、この作品の著作者はA氏であり、著作権者もA氏です。その後、A氏がこの作品の著作権をB氏に譲渡することで、著作権者はB氏となります。一方、著作権をB氏に譲渡したとしても、この作品の著作者はA氏のままです。
著作権(財産権)と著作者人格権の概要と違い
著作権は、狭義の著作権(財産権)と著作者人格権とに分けられます。ここでは、それぞれの概要について解説します。
著作権(財産権)
狭義の著作権である財産権とは、著作物を使って財産的な利益を挙げる権利です。たとえば、アート作品を複写して販売したり、アート作品を転写したクリアファイルを販売したりする権利がこれに該当します。
財産権である狭義の著作権は、譲渡することができます(同61条1項)。そのため、「著作権の譲渡」などという場合は、この財産権が対象とされていることが原則です。
著作者人格権
著作者人格権とは、著作者に帰属する権利です。著作者人格権は著作者の人格的な利益を保護する権利であり、一身に専属します。
そのため、狭義の著作権である財産権とは異なり、譲渡することはできません(同59条)。
つまり、著作者人格権を有するのは必ずその著作物の創作者であり、著作者以外が著作者人格権を有することはないということです。
アート作品に生じる主な著作権(財産権)の種類と例
狭義の著作権である財産権は、一つの権利ではなく、権利の束です。契約によって権利を移転する際は、すべての権利を譲渡することもできる一方で、「複製権だけ」など一部の権利だけを譲渡することもできます。
では、著作権(財産権)にはどのような権利があるのでしょうか?ここでは、アート作品に関連する権利を抜き出して紹介します。
- 複製権
- 上映権
- 公衆送信権・公の伝達権
- 展示権
- 譲渡権
- 貸与権
- 二次的著作物を創作する権利
- 二次的著作物の利用権
複製権
複製権とは、著作物を有形的に再製する権利です。たとえば、アート作品である絵画をコピーしたり模写したりする権利がこれに該当します。
なお、著作権法の規定により、私的利用など一定の場合には、複製権の譲渡を受けなくても著作物の複製が可能です。
上映権
上映権とは、著作物を公にスクリーンやディスプレイに映写する権利です。たとえば、一般向けのセミナーで著作物であるアート作品を、プロジェクターなどを使ってスクリーンに映写することなどがこれに該当します。
なお、インターネット上にあるアート作品をいったんパソコン内に固定したうえで、これをスクリーンに映し出すことも、上映権の範疇であるとされています。セミナーでは「資料に印刷して配賦しなければよい」と考えている人もいるようですが、他人の著作物を無断で公衆に映写するだけでも著作権侵害となり得るため、注意が必要です。
公衆送信権・公の伝達権
公衆送信権・公の伝達権とは、著作物をインターネットで送信したり、放送したり、有線放送したりする権利を指します。たとえば、他人のアート作品を無断で自身のウェブサイトに掲載したりSNSに掲載したりすると、この権利を侵害することとなります。
なお、結果的に誰もそのウェブサイトにアクセスしなかったり結果的に家族しか見なかったりしたからといって、権利侵害とならないわけではありません。インターネット上に載せて公衆がアクセスすれば見られる状態となっている時点で、著作権侵害となります。
展示権
展示権とは、美術の著作物の原作品と、未発行の写真の著作物の原作品を公に展示する権利です。
写真の場合、展示権が発生するのは、未公表写真の原作品に限定されています。一方、絵画など美術の著作物は、公表済の作品であっても展示権の対象となります。
そのため、たとえアート作品を購入したとしても展示権の譲渡を受けていないのであれば、原則として、著作権者に無断で作品の原物を展示することはできません。
ただし、美術の著作物の場合、次の要件をいずれも満たすことで、著作権者から別途承諾を得なくても展示が可能とされています。
- 原作品(オリジナル)の所有者自身か、所有者から同意を得た者が展示すること
- 美術の著作物の原作品を、公園やビルの外壁など一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合でないこと
つまり、アート作品の場合は原作品を購入することで、美術館などでの展示が可能になるということです。
譲渡権
譲渡権とは、著作物の原作品やその複製物を公衆へ譲渡する権利です。たとえば、絵画であるアート作品をコピーして販売するためには、譲渡権が必要となります。
ただし、いったん適法に譲渡された場合は、その後の譲渡には譲渡権は及ばないとされています。そのため、著作物の譲渡権を有する者から著作物の複製を購入した者が、その後購入した複製品を転売する場合は、譲渡権の問題とはなりません。
貸与権
貸与権とは、著作物の複製物を公衆へ貸与する権利です。もっともイメージしやすいのは、レンタルCDサービスやレンタル漫画サービスなどでしょう。
アート作品に貸与権が関連することはあまり考えにくいものの、たとえば絵画のアート作品を複製し、この複製品をレンタルするサービスを展開する場合などには貸与権の問題となります。
二次的著作物を創作する権利
二次的著作物を複製する権利とは、著作物を翻訳、編曲、変形、翻案などする権利です。二次的著作物とは、「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物」を指します(同2条1項11号)。
たとえば、立体的なアート作品をもとに絵画を制作したり、絵画のアート作品を写真に撮ったり、絵画のアート作品に描かれた人物をデフォルメしたイラストを制作することなどが該当します。
二次的著作物の利用権
二次的著作物も著作物の一つであり、独自の著作物として著作権の対象となります。ただし、二次的著作物の「もと」となった元の著作権の著作権者は、二次的著作物について、二次的著作物の著作権者が有するのと同じ権利を有します。
たとえば、A氏が制作したアート作品をもとにB氏が二次的著作物であるイラストを制作した場合、B氏が制作したイラストを使用したいC氏はB氏の許諾を得るだけでは足りず、原則としてA氏の許諾も必要となるということです。
アート作品で二次的著作物の利用権が問題となることはさほど多くない一方で、たとえば漫画をもとにアニメ化された作品や小説をもとに漫画化された作品などは権利関係が絡み合い、処理が複雑となる傾向にあります。
アート作品に生じる著作者人格権の種類と例
次に、アート作品に生じる著作者人格権を紹介します。著作者人格権には「公表権」と「氏名表示権」、「同一性保持権」の3つがあります。それぞれの概要について解説します。
なお、先ほどお伝えしたように、著作者人格権は譲渡することができません。そのため、たとえ契約書で「著作者人格権を譲渡する」と定めても、移転の効果は生じないため注意が必要です。現実的には、契約書で「著作者人格権を行使しない」などと定めることが多いでしょう。
公表権
公表権とは、未公表の著作物を公表するかしないかどうか決めるほか、公表するとすればいつ、どのような方法で公表するかを決める権利です。
たとえば、未公表のアート作品(絵画)がある場合、たとえこの絵画を購入したり絵画の著作権を譲り受けたりしたとしても、著作者以外がこれを無断で公表することはできません。
氏名表示権
氏名表示権とは、自分の著作物を公表するときに著作者名を表示するかしないか、表示するとすれば、実名と変名のいずれを表示するかを決めることができる権利です。
たとえば、アート作品である絵画を購入し著作権も譲り受けた者がこの著作権を展示する場合、著作者の氏名を添えて展示するかどうかは、著作者が決められるということです。
また、著作者が変名(ペンネーム)の表示を希望しているにもかかわらず、展示する際に無断で著作者の本名を表示すれば氏名表示権を侵害し、損害賠償請求の対象となる可能性があります。
同一性保持権
同一性保持権とは、著作物の内容や題号を意に反して無断で改変されない権利です。アート作品を譲り受けたとしても、無断で改変ができるわけではありません。
たとえば、著作権の譲渡を受けたからといってアート作品に勝手に色を塗り足したり勝手にタイトルを変えたりすれば、同一性保持権を侵害することとなります。
アート作品にまつわる著作権トラブルを避ける対策
著作権制度はやや複雑であるためか、アートにまつわる著作権トラブルは少なくありません。では、アートにまつわる著作権トラブルを避けるには、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?
最後に、著作権トラブルを避けるための主な対策を2つ解説します。
- アート作品にまつわるビジネスを展開する際は弁護士へ相談する
- 契約書を作り込み齟齬をなくす
アート作品にまつわるビジネスを展開する際は弁護士へ相談する
1つ目は、あらかじめ弁護士へ相談することです。
著作権は非常に複雑な権利であり、誤解も少なくありません。その誤解をもとに安易な処理をしてしまうことが、トラブルの原因となり得ます。
たとえば、よくある誤解として、著作権の譲渡を受ければ著作者には何ら権利が残らないというものが挙げられます。しかし、先ほど解説したように、たとえ著作権を移転しても、著作者人格権は著作者に残ります(同59条)。
そのため、著作権を譲り受けた者がアート作品を自分が描いたと偽って展示したり無断でタイトルを変えて展示したりすれば、著作者から権利侵害を主張される可能性があります。
また、契約書で「著作権をすべて譲渡する」とさえ書けば、すべての権利が移転すると考えるかもしれません。
しかし、著作物を翻案(変形や脚色、映画化など)する権利や二次的著作物の利用権を「すべて」の中に含めることはできず、これらの権利も移転したい場合は、これらの権利について契約書に個別で明記する必要があります(同61条2項)。
このように、著作権については注意点が多く、実際のビジネスにおける権利処理には専門知識が不可欠です。後のトラブルを避けるため、アートにまつわるビジネスを展開する際は著作権にくわしい弁護士のサポートを受けるようにしてください。
契約書を作り込み齟齬をなくす
2つ目は、必ず契約書を作成することです。
著作権にまつわるトラブルは、双方の思い違いから生じるケースも少なくありません。
たとえば、A氏がアート作品(絵画)の制作を画家であるB氏に依頼した場合、何ら契約を交わさなければ、作品の著作権は原則としてB氏に残ります。しかし、対価を払って制作を依頼したA氏としては、額に入った絵画という「物」を譲り受けたことで、著作権も当然に譲渡されたと誤解する可能性があります。
その結果、権利侵害の意識のないままにA氏がこの絵画をプリントしたグッズを制作してB氏に無断で販売すれば、トラブルの原因となるでしょう。
残念なことに、著作権について正しく理解している人はさほど多くありません。双方の齟齬をなくしてトラブルを未然に防ぐため、契約書を交わしてあらかじめ認識を合わせておくことが必要です。
まとめ
アートにまつわる著作権について解説しました。
著作権は主に、財産権(狭義の「著作権」)と著作者人格権とに分類されます。さらに、狭義の著作権も一つの権利ではなく権利の束であり、一部の権利だけを譲渡することも可能です。
このように、著作権は細分化されており、適切に権利処理をすることには困難が伴います。アート作家としては想定外の利用をされないために、アートを活用したい側としては目的を果たすために必要な権利を漏れなく譲り受けるために、あらかじめ弁護士へご相談ください。
伊藤海法律事務所の代表である伊藤海は、弁護士のほか弁理士資格も有しており、著作権など知的財産の保護や活用に関するサポートを特に強みとしています。アートにまつわる著作権をきちんと処理したい場合や、アートに関して著作権トラブルが生じている場合などには、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。