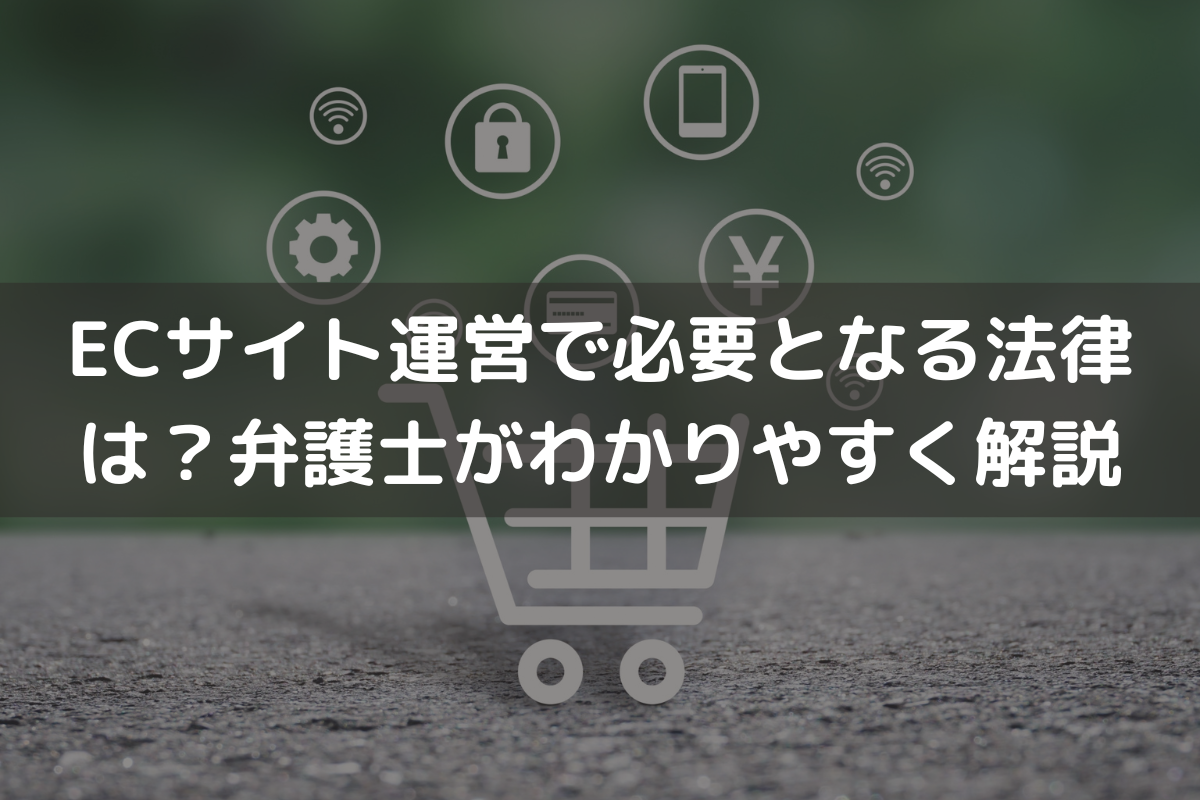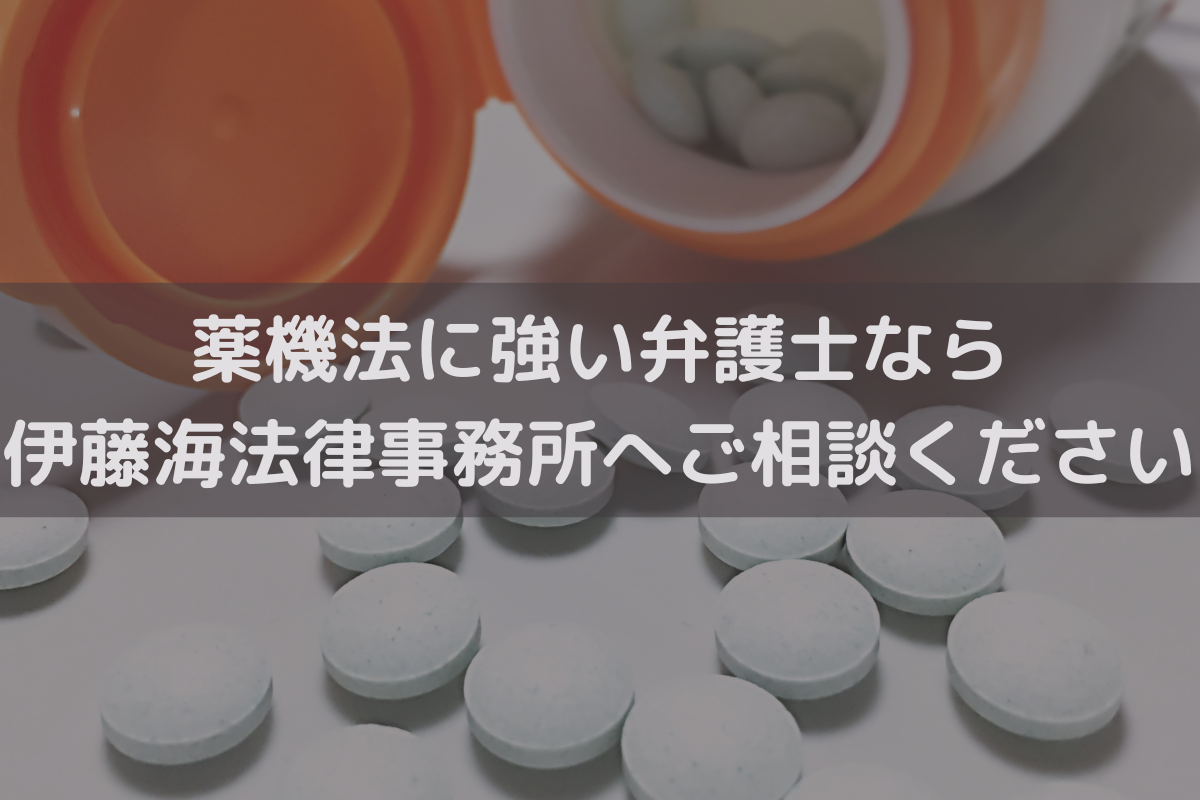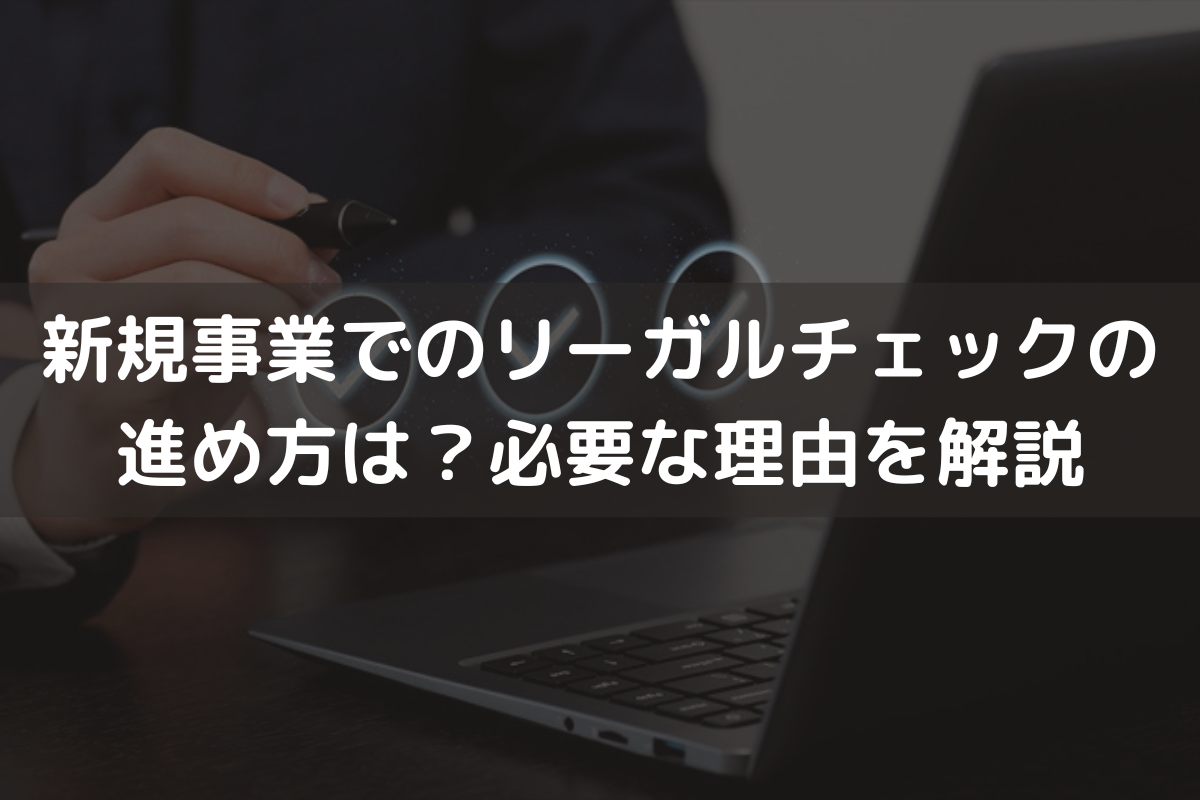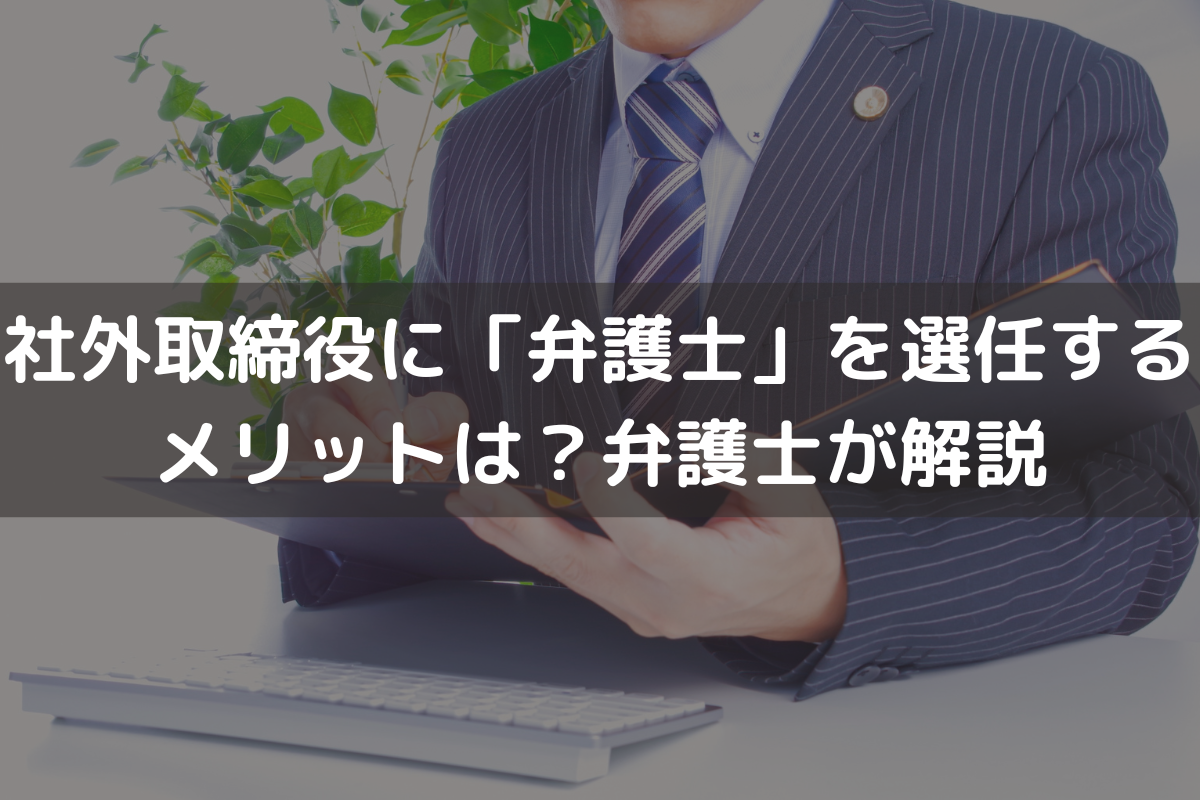若年層を中心にインターネット上での買い物に抵抗感を持たない人が増えており、ECサイトを解説する事業者や個人も増えています。ECサイトが軌道に乗れば大きな副収入となる可能性が生じるほか、自身が営む実店舗との相乗効果で売上が増加する効果なども期待できるでしょう。
しかし、ECサイトには実店舗とは異なる規制も多く、ECサイトを開設するにあたっては関連する法律やガイドラインなどを理解しておかなければなりません。今回は、ECサイトの開設にあたって知っておきたい法律の概要について、インターネット法務に詳しい弁護士が解説します。
ECサイト運営者が知っておくべき法律1:民法
ECサイトの運営にあたって知っておくべき法律の1つ目は民法です。はじめに、民法の概要とECサイト運営にあたって必須となる「定型約款」などについて解説します。
民法とは
民法とは、私人間(個人対個人や、法人対個人、法人対法人など)の権利や義務について、ベースとなる事項をまとめた法律です。
たとえば、お店で買い物すると、対価と引き換えに商品を受け取ることが可能となります。
また、お金を借りた場合は、期日までに返済しなければなりません。このように、民法には契約や権利義務の基本的な事項が規定されています。
民法は契約や権利義務の基礎となる法律であるため、ECサイトの運営にあたって他の法令や約款などに規定がない場合は、民法に立ち返って規定を確認することとなります。
民法に規定のある利用規約(定型約款)とは
民法の中でもECサイト運営社が特に知っておくべきなのは、定型約款に関する規定です。定型約款とは、事業者が顧客などの不特定多数の者と同じ内容の契約をする際に用いる、定型的な契約条項を指します。ECサイトの利用規約は、原則としてこの定型約款に該当します。
原則として、契約は当事者間で個別に締結するものです。しかし、ECサイトなど事業者が不特定多数の者と契約すべき場合において、個々のユーザーごとに契約書を取り交わすことは現実的ではありません。
そこで、ECサイトの運営者など事業者側があらかじめ定型的な約款を作成し、個々のユーザーがその定型約款を契約の内容とすることについて同意した場合は、その定型約款の個々の条項についても合意したものとみなされることとされています(民法548条の2 1項)。
つまり、ユーザーが合意することで、ECサイトの運営者が作成してウェブサイト上で表示された定型的な約款の内容が、事業者と個々のユーザーとの契約条項になるということです。
また、変更が相手方の一般の利益に適合するなど一定の要件を満たすことで、個々のユーザーから合意を得ることなく、事業者が定型約款の内容を変更することも可能となります。
利用規約をECサイトに掲載する際の注意点
利用規約をECサイトに掲載する際は、その利用規約が定型約款となる要件から外れないよう注意してください。利用規約が提携約款となる(つまり、個々のユーザーが利用規約の内容について合意したものとみなされる)のは、次の要件をいずれも満たした場合のみです。
- 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき
- 事業者が、あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき
たとえば、ウェブサイトの片隅に利用規約へのリンクを張っているだけでは、これについてユーザーが合意したとみなすことは困難でしょう。
利用規約を定型約款とするためには、ユーザーがそのECサイトの利用登録などをするにあたって「本利用規約の内容を契約内容とすることに合意します」などのチェックボックスを設け、これにユーザーがチェックを入れてクリックし、さらにその後表示される確認画面から再度クリックしないと登録ができないようにするなどの画面設計が必要となります。
また、「どうせ読まないだろう」などとの考えから、ユーザーが一方的に不利となる内容を規約に盛り込むことは避けるべきです。なぜなら、相手方の利益を一方的に害すると認められる条項については、合意をしなかったものとみなす(つまり、その部分は無効になる)こととされているためです(同2項)。
そのほか、消費者に一方的に不利益となる条項をこっそり盛り込むと、これがSNSなどで拡散され「炎上」しユーザーが離れてしまうリスクも高くなります。
ECサイト運営者が知っておくべき法律2:電子契約法
ECサイトの運営にあたって知っておくべき法律の2つ目は、電子契約法です。電子契約法は2024年1月現在、3条しかない法律です。
電子契約法とは
電子契約法とは、ECサイトでの商品購入などの際に、民法の原則を一部変更して消費者を保護するために設けられている法律です。
電子契約法の概要
2024年1月現在、電子契約法では電子商取引の場合において、民法による錯誤の規定を修正する規定のみが残っています。
民法では、表意者が意思表示に対応する意思を欠く場合、その錯誤が法律行為の目的や取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、意思表示を取り消すことができるとされています(民法95条1項)。
たとえば、ある消費者が商品を1つだけ買うつもりであったところ、錯誤(勘違い)によって11個買うと意思表示をする場合などがこれに該当します。ただし、その錯誤が表意者の重大な過失による場合は、原則として取り消すことができません(同3項)。
一方、ECサイトなどによる電子商取引では、クリックミスや同じボタンを連打してしまうことなどにより、注文ミスが起こりやすくなります。民法の規定をそのまま適用して消費者に重過失があった場合に取り消しができないこととなれば、うっかりミスによるご注文が増加してしまうでしょう。
また、悪質なサイト運営者が、消費者による大量注文のミスを誘うようなUI(ユーザーインターフェース)を構築してしまうかもしれません。
そこで、電子契約法では事業者と消費者との契約に限り、次の場合においては、たとえ消費者に重過失があっても取り消しができることとされています(電子契約法3条)。
- 消費者がそもそも申し込むつもりがなかったとき(例:申し込むつもりがなかったのに、画面に誤って触ってしまい商品を注文した)
- 消費者が本来の意思とは異なる意思表示をしたとき(例:商品を1個買うつもりが、誤って11個と入力して申し込んでしまった)
しかし、このような際にいつでも契約が取り消されるおそれがあるとすれば、事業者は安心してECサイトを運営することができません。そのため、次のいずれかの場合には民法の原則に立ち返り、消費者に重過失があった場合には錯誤による取り消しは認められないこととされています。
- 事業者がその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込みもしくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合
- その消費者から事業者に対して「1」の措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合
つまり、消費者が注文情報を入力した後「申込み」などのボタンを押した時点ですぐに申込みを成立させるのではなく、確認画面を表示するなどワンクッションを置いてから申込みを成立させることで、重過失のある消費者からの錯誤取り消しはできなくなるということです。
多くのECサイトでは注文から注文成立までの間に「確認画面」などを設けていますが、これは、この電子契約法の規定によるものです。
ECサイト運営者が知っておくべき法律3:特定商取引法
3つ目は、特定商取引法です。特定商取引法の知識は、ECサイトの開設や運営にあたって特に不可欠といえます。
特定商取引法とは
特定商取引法とは、事業者による違法や悪質な勧誘行為等を防止して、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。
特定商取引法は一定の商取引のみを規制対象としており、そのうちの1つに「通信販売」があります。通信販売とは、販売業者などが郵便などによって売買契約や役務提供契約の申込みを受けて行う商品の販売などを指し、ECサイトによる商品の販売は原則としてこの通信販売に該当します。
ECサイトに掲載すべき「特定商取引法に基づく表記」の概要
特定商取引法の規制により、ECサイトなどでは一定の事項を表示しなければなりません。まず、商品の広告をする際には、原則として次の事項を表示する必要があります。
- 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
- 代金(対価)の支払時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
- 契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。)
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
- 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
- 事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所及び電話番号
- 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容及びその額
- 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
- いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
- 契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件又は提供条件
- 商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
- 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
- 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
また、ECサイトから申込みをする際には、次の情報を確認できる状態にする必要があります。
- 分量
- 販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
- 代金(対価)の支払時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
- 契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。)
具体的な表示方法などがわからない場合は、弁護士などへご相談ください。
その他最低限知っておくべき特定商取引法による規制
特定商取引法には、他にもECサイト運営にあたって注意すべき規制が設けられています。
たとえば、通信販売の申込みの撤回等によって契約当事者双方に原状回復義務が課された場合に、事業者が代金返還など債務の履行を拒否したり遅延したりすることを禁止する規定や、顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止規定などです。
通信販売にあたって注意すべきポイントは、消費者庁が運営する「特定商取引法ガイド」にまとめられています。こちらも確認しておくことをおすすめします。
ECサイト運営者が知っておくべき法律4:個人情報保護法
ECサイト運営社が知っておくべき法律の4つ目は、個人情報保護法です。
個人情報保護法とは
個人情報保護法とは、個人情報の有用性に配慮しつつも個人情報の保護をはかるための法律です。
ECサイトの運営にあたっては、顧客の個人情報を取得する機会が少なくありません。そのため、個人情報誤報に関する理解は不可欠です。
ここでは、ECサイトに掲載すべきプライバシーポリシーの概要に絞って解説します。
ECサイトに掲載すべきプライバシーポリシーの概要
プライバシーポリシーとは、事業者における個人情報の取り扱い方針を定めたものです。ECサイトを開設する際はプライバシーポリシーを定め、トップページなどからリンクを貼ることが一般的です。
実は、プライバシーポリシーの公開は個人情報保護法で直接定められているものではありません。しかし、個人情報保護法には本人への通知か公表をすべきとされている事項が多く定められています。
そこで、プライバシーポリシーに所定の事項を盛り込んで公表することで、本人に対して直接個々に通知すべきケースを最小限に抑えることが可能となります。
個人情報保護法は改正が多い法律の一つであり、改正後に応じてプライバシーポリシーも改訂する必要があります。プライバシーポリシーの策定や改訂でお困りの際は、弁護士へご相談ください。
ECサイト運営者が法律違反をしないための対策
ECサイトの運営者が法律違反をしてしまうと、罰則の適用対象となるほか、消費者からの信頼が揺らいでしまう事態となりかねません。では、ECサイトの開設や運営にあたって法令違反しないようにするには、どのような対策を講じればよいのでしょうか?最後に、主な対策を3つ紹介します。
- 各法令とガイドラインを読み込む
- ECサイト開設時に弁護士へ相談する
- 弁護士への相談体制を構築しておく
各法令とガイドラインを読み込む
1つ目は、関連する法令やガイドラインをあらかじめ読み込んでおくことです。
これまで解説したように、ECサイトの運営にあたっては特定商取引法や個人情報保護法などさまざまな法令を理解しておかなければなりません。そこで、関連する法令やガイドラインを一読し、理解しておくことをおすすめします。
特に、ガイドラインには具体的な状況に即した記載がされているため、法令よりも理解しやすいでしょう。
また、特定商取引法や個人情報保護法は消費者庁や個人情報保護委員会などがホームページ上でパンフレットなどの資料も公表しているため、こちらにも目を通すと理解が深まりやすくなります。
ECサイト開設時に弁護士へ相談する
2つ目は、ECサイトの開設時に弁護士へ相談することです。
先ほど紹介した関連法令は、あくまでも代表的なものだけであり、事業の形態や販売するものの種類などによっては他の法令も関連します。法律は数多く存在しており、自身が営むECサイトに関連する法令をすべて洗い出すだけでも一苦労でしょう。また、法令やガイドラインを読み込んでも、具体的にどうすべきか判断が難しいこともあると思います。
しかし、「知らなかった」や「誤解していた」ことを理由に、放置違反が許されるわけではありません。そのため、ECサイトを開設する際は、インターネット法務に強い弁護士のサポートを受けるようにしてください。
弁護士へ相談することで自身が開設しようとするECサイトに即したアドバイスを受けられるほか、各種規定の作成やレビューなどのサポートを受けることも可能となります。
弁護士への相談体制を構築しておく
3つ目は、弁護士への相談体制を構築しておくことです。
ECサイトの規約や法令に基づく表示などは一度作成すれば完璧ということではなく、法改正などに対応して適宜改訂していかなければなりません。また、ECサイトを運営して事業を行うと、思わぬトラブルが生じることもあるでしょう。
そのような際にスムーズに対応できるようにするため、インターネット法務に詳しい弁護士と顧問契約を締結するなど、弁護士へ相談できる体制を構築しておくと良いでしょう。
まとめ
ECサイトの開設にあたって知っておくべき法令を紹介するとともに、それぞれの概要について解説しました。
ECサイトの運営には民法のほか、特定商取引法や個人情報保護法などさまざまな法令が関連します。また、これら以外にも状況に応じてさまざまな法令を確認し、遵守しなければなりません。
しかし、自社のみで関連する法令を洗い出し、実際の業務に劣り込めるレベルにまで理解を深め、かつ改正などのキャッチアップを続けることは容易なことではないでしょう。そのため、ECサイトを開設するにあたっては、弁護士のサポートを受けるようにしてください。
伊藤海法律事務所ではインターネット法務に力を入れており、ECサイト開設にあたってのリーガルサポートを行っています。ECサイト開設にあたって法令上の問題がないか確認して欲しい場合や規約などの作成を依頼したい場合、ECサイト運営にあたって相談できる弁護士をお探しの場合などには、伊藤海法律事務所までまずはお気軽にご相談ください。