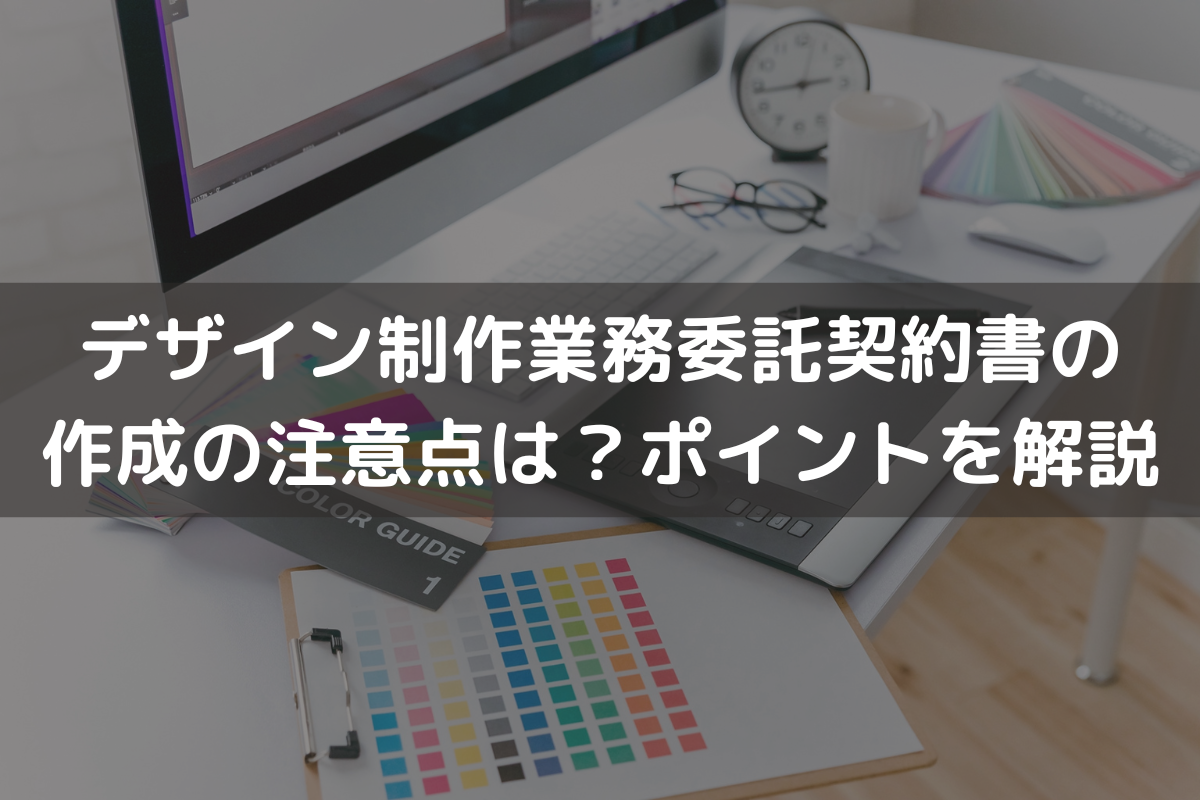デザイン制作は社内で行うこともできるほか、外部の企業や個人に委託することも可能です。デザインの制作を委託する際は、必ず契約書を交わしておきましょう。契約書がなければ、業務範囲や知的財産権の帰属などに関してトラブルに発展するおそれがあるほか、トラブル発生時の解決も難航するおそれがあるためです。
では、デザイン制作業務委託契約書とはどのような契約書なのでしょうか?また、デザイン制作業務委託契約書には、どのような条項を設ける必要があるのでしょうか?今回は、デザイン制作業務委託契約書の概要や設けるべき条項、デザイン制作業務委託契約書の作り方などについて弁護士がくわしく解説します。
なお、当事務所(伊藤海法律事務所)はカルチャー・エンターテイメント法務に特化しており、デザイン制作業務委託契約書の作成やレビューについて豊富な実績を有しています。デザイン制作業務委託契約書について相談できる弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご連絡ください。
デザイン制作業務委託契約書とは
デザイン制作業務委託契約書とは、デザイン会社やフリーのデザイナー(以下、この記事ではまとめて「デザイナー」と呼びます)にデザイン制作を委託するにあたって取り交わす契約書のことです。
契約の本旨にあたるデザイン制作を委託する旨に加え、委託料や知的財産の帰属などについても定めることが一般的です。
デザイン制作業務委託契約書の種類
デザイン制作業務委託契約には、民法上の「請負契約」に該当する場合と「準委任契約」に該当する場合があります。ここでは、それぞれの概要と主な違いについて解説します。
取り交わす契約がいずれの性質を持っているのかを把握したうえで、民法の規定を確認しておくと良いでしょう。契約書に記載されていない事項は、原則として民法の規定が適用されることになるためです。また、民法の規定を修正したい場合には、契約書で修正すべき事項を明記しなければなりません。
請負契約
請負契約とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって効力を生ずる契約です(民法632条)。
請負契約では「過程」ではなく、仕事の完成(成果物の納品)という「成果」が重視されます。そのため、受託者であるデザイナーは仕事の完成義務を負い、報酬は目的物の引き渡しと同時に支払うことが原則です(同633条)。
また、過程を重視しないため、再委託は原則として自由とされています。端的にいえば、「どのような方法を使っても良いので、契約に適合したデザインを納期までに納品してください」というのが請負契約の基本です。
準委任契約
準委任契約とは、当事者の一方が法律行為ではない事務をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約です(同656条、643条)。
請負契約とは異なり、準委任契約は「成果」よりも「過程」が重視されます。そのため、受任者には善管注意義務(善良な管理者としての注意をもって事務処理を遂行する義務)が課されます(同644条)。
「過程」が重視される契約であるため、委任者の許諾を得たときとやむを得ない事由があるときを除き、再委託はできません。また、報酬の請求時期は委任事務の履行後が原則であるものの、期間によって報酬を定めることも可能です。
デザイン制作業務委託契約書が必要となるケース
デザイン制作業務委託契約書が必要となるのは、デザイン制作を外部のデザイナーなどに委託する場合です。
デザイン制作を委託する際にはまず、納期や報酬額、知的財産権の帰属などに関する基本事項について双方で合意をまとめます。合意がまとまったら、どちらか一方(一般的には、発注者)が契約書の原案を作成します。
そのうえでこの原案を提示し、必要に応じて条項修正の交渉などを行い、最終的な合意内容で契約書を取り交わすという流れです。デザイン制作を委託するにもかかわらず契約書を取り交わさなければ、次で解説するようにさまざまなトラブルの原因となります。
デザイン制作業務委託契約書の作成をご検討の際は、伊藤海法律事務所までご相談ください。
デザイン制作業務委託契約書がないことによる主なトラブル
デザイナーにデザイン制作業務を委託するにあたって、契約書を交わさないこともあるようです。しかし、デザイン制作業務委託契約書がない場合、さまざまなトラブルが生じるおそれがあります。
ここでは、契約書がないことから生じる可能性がある主なトラブルを4つ紹介します。
- 委託業務の範囲にまつわるトラブル
- 委託料の支払いに関するトラブル
- 知的財産の帰属にまつわるトラブル
- 一方的な中断にまつわるトラブル
委託業務の範囲にまつわるトラブル
デザイン制作業務委託契約書がない場合、委託した業務の範囲について齟齬が生じ、トラブルに発展するおそれがあります。
たとえば、修正の依頼時にデザイナーが追加報酬を請求したところ、委託者が軽微な修正は当初の報酬内に含まれていると主張してトラブルになる場合などが想定されます。また、委託者がマスターデータの納品を求め、デザイナーがマスターデータの引き渡しについて追加報酬を請求することでトラブルとなる場合もあるでしょう。
委託料の支払いに関するトラブル
デザイン制作業務委託契約書がない場合、委託料の支払いに関してトラブルとなるおそれがあります。
たとえば、口頭で合意した金額について、納品後に委託者から値下げを要求される場合などが想定されます。また、委託者が対価を一向に支払わず、訴訟を提起しようにも契約成立の証明がハードルとなるリスクもあるでしょう。
知的財産の帰属にまつわるトラブル
デザイン制作業務委託契約書がない場合、知的財産権の帰属についてトラブルとなるおそれがあります。
別段の取り決めがない場合、デザインの著作権はデザイナー側に帰属します。しかし、委託者が「対価を支払ってデザイン制作を依頼したのだから、著作権は自社に帰属するはずだ」と誤解しているケースも少なくありません。中には、納品後に著作権が自社に帰属しないことに気付いた委託者から、対価の減額を要求される場合もあるでしょう。
契約書で知的財産権の帰属を明記しておくことで、このような齟齬を防ぎやすくなります。
一方的な中断にまつわるトラブル
デザイン制作業務委託契約書がない場合、一方的な中断によってトラブルが生じるおそれがあります。
口頭などでの契約成立後に、デザイナー側がある日突然音信不通となる場合のほか、委託者と連絡が取れなくなる場合もあるでしょう。このような場合であっても、契約書を交わしていれば、訴訟などで解決をはかることが可能です。
一方、契約書がなければ契約が成立していたことの立証が難しく、解決が困難となるおそれがあります。
デザイン制作業務委託契約書の主な条項と作成ポイント
デザイン制作業務委託契約書は、どのような点に注意して作成すればよいのでしょうか?ここでは、主な条項と作成のポイントを解説します。
- 契約の目的
- 検収と修正対応
- 対価の額と支払のタイミング
- 再委託の可否
- 知的財産権の帰属
- 非侵害保証
- 損害賠償
- 禁止事項
なお、契約書に設けるべき条項や最適な内容は、契約の目的や状況、当事者の立場などによって異なります。そのため、実際にデザイン制作業務委託契約書を交わそうとする際や相手方に提示する原案を作成しようとする際は、あらかじめ弁護士へご相談ください。
契約の目的
デザイン制作業務委託契約書では、はじめに契約の目的を記載します。
委託する業務の内容に疑義が生じないよう、できるだけ具体的に記載してください。記載した内容が、次で解説する「検収」に合格するか否かの基準となるためです。
契約書にすべて記載することが難しい場合は別途仕様書を作成し、契約書では「別紙仕様書のとおりとする」などと規定する場合もあります。
検収と修正対応
デザイン制作業務委託契約におけるデザイナーの義務履行については、次の2つのパターンが考えられます。
- デザインを委託者に引き渡した時点で終了する
- デザインの引き渡し後、委託者による検収が完了した時点で終了する
一般的には、このうち「2」のケースが多いでしょう。契約書では、どの段階で義務履行とするのかを明記してください。
また、実務上は「納品したもののいっこうに検収してもらえない」という事態も想定されます。これに備え、「納品後〇日以内に修正連絡がない場合は、検収に合格したものとみなす」などの一文を入れておくとよいでしょう。
併せて、修正が生じた場合の対応義務や、修正が生じた場合の報酬(発生の有無や、発生する場合は報酬の定め方など)についても明記しておくことをおすすめします。
対価の額と支払のタイミング
契約書では、対価の額と支払いのタイミングについて明記しましょう。対価については、主に次の3つのパターンが想定されます。
- 一括払いのみ
- 頭金+ロイヤリティ
- ロイヤリティのみ
ロイヤリティの授受がある場合は、ロイヤリティの計算方法についても明記してください。計算方法は、誰が計算しても同じ結果となるよう明確に定めることがポイントです。
再委託の可否
デザイン制作業務委託契約書では、再委託の可否について明記しましょう。
先ほど解説したように、請負契約である場合と準委任契約である場合とで、再委託の考え方が異なります。トラブルが生じないよう、再委託を禁止する場合であっても再委託を許諾する場合であっても、その旨を明記することをおすすめします。
また、再委託の許諾について、「委託者の事前承諾」などの条件を設ける場合には、その旨も明記してください。
知的財産権の帰属
先ほど解説したように、デザイン制作業務委託契約では知的財産権に関するトラブルが少なくありません。そのため、制作したデザインにかかる知的財産権の帰属について、契約書に明記することが必要です。
契約書に特に記載がなければ、デザインの著作権は原則としてデザイナーに帰属します。
ただし、実際には、委託者がある程度アイデアを出してデザイナーがこれに修正を加えるなどしてデザインを制作する場合もあるでしょう。このように、デザインの基幹となるアイデアを委託者が出した場合などには、委託者に著作権が帰属する余地もあります。
権利帰属について後にトラブルが生じないよう、著作権など知的財産権の帰属については事前に当事者間で認識をすり合わせたうえで、契約書にも明記してください。
非侵害保証
デザイン制作の業務委託契約書では、非侵害保証条項を入れることが一般的です。非侵害条項とは、成果物が第三者の知的財産権を侵害していないことについて、デザイナーが保証する旨の条項です。
なお、実際にはデザイナーが意匠権や商標権などの産業財産権を侵害していないことまでを保証するのは、荷が重過ぎるとの見方もあります。これらは、仮にデザイナーがその第三者の意匠権や商標権などの存在をまったく知らず、偶然似た場合であっても侵害となり得るためです。
一方、著作権侵害には原則として依拠性があること(つまり、模倣したこと)が要件となるため、デザイナーが非侵害を保証しやすいといえます。そのため、「第三者の知的財産権を侵害していない」ことまで広くは保証せず、「第三者の著作権を侵害していない」ことだけを保証する条項とすることもあります。
損害賠償
金額や期間の制限なく損害賠償責任を負う事態は、双方ともに避けたいことでしょう。そのため、デザイン制作業務委託契約書に、損害賠償の上限額を設けることを検討します。
損害賠償の上限額は、委託料相当額などとするケースが多いでしょう。併せて、損害賠償責任を負う期間について制限を記載することもあります。
禁止事項
デザイン制作業務委託契約書では、禁止事項を定めます。禁止事項として定められることが多いのは、次の内容などです。
- 第三者のデザインの模倣
- 競合他社のデザイン業務を同時並行すること
- 再委託
禁止事項の内容は、状況や目的などに応じて個々に検討することをおすすめします。契約書の内容についてお困りの際は、弁護士へご相談ください。
デザイン制作業務委託契約書を確認する主な視点
相手方からデザイン制作業務委託契約書の原案を提示された場合、内容を確認せずそのまま押印することは避けるべきです。必ず内容を確認し、内容に同意できる場合のみ押印へ進んでください。
万が一、自社(自身)にとって都合の悪い内容となっていても、押印をした以上は「知らなかった」との主張は困難となるためです。ここでは、デザイン制作業務委託契約書で、特に確認すべき事項を3つ紹介します。
- 委託する業務の内容は明確となっているか
- トラブル発生時にどのような対応がとれるか
- 知的財産は自社が望む利用ができる内容で処理されているか
委託する業務の内容は明確となっているか
1つ目は、委託する業務の内容が、契約書で明確となっているか否かです。業務内容の記載があいまいであると、対応範囲や追加料金の発生について齟齬が生じてトラブルとなるおそれがあります。
また、デザイナー側は、自身が行う予定のない業務内容が記載されていないか、慎重に確認してください。相手方が、差し入れた契約書について「いつも使っているテンプレートだから、関係ない内容も書いてあるけど気にしないで」などと説明することもあるでしょう。しかし、契約書に記載がある以上は、記載された業務への対応を求められる可能性があります。
トラブル発生時にどのような対応がとれるか
2つ目は、トラブル発生時に自社(自身)がどのような対応がとれるかです。契約書のほか、民法など関連する法令を確認したうえで、とれる対応を確認しておきましょう。
あらかじめ確認しておくことでトラブル発生時の対応がスムーズとなるほか、事前に契約書の修正を交渉することも可能となります。
知的財産は自社が望む利用ができる内容で処理されているか
3つ目は、デザインの知的財産権について、自社が想定した活用が可能な内容で処理されているか否かです。知的財産について契約書内で適切な処理がされていなければ、自社の望む利用ができなくなるおそれがあります。
知的財産権については注意点が少なくありません。そのため、特に重要なデザイン制作業務委託の場面では、あらかじめ弁護士に確認を受けることをおすすめします。
デザイン制作業務委託契約書の作り方
デザイン制作業務委託契約書は、どのような方法で作成すれば良いのでしょうか?ここでは、デザイン制作業務委託契約書の2パターンの作り方を解説します。
- テンプレートを利用する
- 弁護士に依頼する
テンプレートを利用する
インターネットや書籍などを探すと、デザイン制作業務委託契約書のひな型が見つかることでしょう。これをもとに作成するのが1つ目の方法です。
しかし、テンプレートはあくまでも一般的なケースを想定して作られたものであり、その内容が必ずしも自社の契約実態に即しているとは限りません。そのため、テンプレートを活用する場合であってもそのまま流用することは避けてください。
内容を理解しないままテンプレートを流用することは、トラブルの原因となりかねないためです。また、条項が自社にとって不利な内容となっていることに気付かないまま締結に至ってしまうリスクもあるでしょう。
テンプレートを活用してデザイン制作業務委託契約書を制作しようとする際は、まずは記載されている条項を熟読して理解する必要があります。そのうえで、契約実態に即していない箇所を実態に合わせて作り変えます。
なお、複数の条項が相互に関連していることも多いため、1つの条項に修正を加えることで他の条項との整合性がとれなくなる可能性があります。そのため、1つの条項を修正したら、これと連動して修正すべき事項はないか確認すべきでしょう。
弁護士に依頼する
デザイン制作業務委託契約書は、弁護士に依頼して作成してもらうことも可能です。これが2つ目の方法です。
先ほど解説したように、テンプレートを活用しても、自社だけで適切なデザイン制作業務委託契約書を作成することは容易ではありません。問題のある内容で契約を締結してしまうと、トラブルの原因となったり、トラブル発生時に不利となったりするおそれが生じます。
そのような事態を避けるため、デザイン制作業務委託契約書の作成は弁護士に依頼するのがおすすめです。弁護士に依頼することで、契約実態に合った的確な契約書の作成が可能となるほか、自社にとって有利な条項をバランスよく盛り込むことが可能となります。
デザイン制作業務委託契約書の作成を依頼できる弁護士をお探しの際は、伊藤海法律事務所までご相談ください。
デザイン制作業務委託契約書に関する印紙
一定の契約書には印紙を貼付することで、印紙税を納めなければなりません。そして、印紙の要否や印紙税の金額は、契約書の内容によって異なります。
まず、デザイン制作業務委託契約書が「準委任契約」に該当するものである場合、印紙を貼る必要はありません。準委任契約は、印紙税の課税対象外であるためです。
一方で、デザイン制作業務委託契約書が「請負契約」に関するものである場合、請負金額の額に応じて次の印紙の貼付が必要となります。
| 契約書に記載された契約金額 | 印紙の額 |
| 契約金額の記載がないもの | 200円 |
| 1万円未満 | 不要 |
| 1万円以上100万円以下 | 200円 |
| 100万円超200万円以下 | 400円 |
| 200万円超300万円以下 | 1千円 |
| 300万円超500万円以下 | 2千円 |
| 500万円超1千万円以下 | 1万円 |
| 1千万円超5千万円以下 | 2万円 |
| 5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
| 1億円超5億円以下 | 10万円 |
| 5億円超10億円以下 | 20万円 |
| 10億円超50億円以下 | 40万円 |
| 50億円超 | 60万円 |
なお、印紙税は紙の契約書を取り交わした場合に必要となる税金です。電子契約である場合には、請負契約であっても印紙税を納める必要はありません。
デザイン制作業務委託契約書を作る際の注意点
デザイン制作業務委託契約書を作る際は、どのような点に注意する必要があるのでしょうか?ここでは、主な注意点を2つ解説します。
- 契約実態に合った内容とする
- トラブル発生時から「逆算」をして条項を検討する
契約実態に合った内容とする
デザイン制作業務委託契約書は、契約実態に合致した内容で作成する必要があります。「契約書にはこのように書いてあるけれど、これとは異なる内容で口頭で合意した」などのケースでは、その齟齬が原因でトラブルに発展するかもしれません。
そのため、デザイン制作業務委託契約書にあたっては、テンプレートをそのまま流用することなどは避け、実態に合った内容で契約書を作成しましょう。
トラブル発生時から「逆算」をして条項を検討する
デザイン制作業務委託契約書が真価を発揮するのは、トラブルが発生したときです。そのため、トラブルの発生から「逆算」をして契約内容を検討すべきでしょう。
たとえば、「デザイナーによる著作権侵害は絶対に避けたい、著作権侵害が判明した場合には即刻契約を解除したい」と考えるのであれば、非侵害条項を設けるとともに、違反時には催告なく解除する条項を設けるなどです。
とはいえ、さまざまなトラブルを想定し、それに対応する条項を1つずつ検討することは容易ではありません。そのため、デザイン制作業務委託契約書の作成は無理に自社だけで行うのではなく、弁護士のサポートを受けて行うと良いでしょう。
デザイン制作業務委託契約書の作成は伊藤海法律事務所にご相談ください
デザイン制作業務委託契約書を作成する際は、伊藤海法律事務所までご相談ください。最後に、伊藤海法律事務所の主な特長を4つ紹介します。
- カルチャー・エンターテイメント法務に特化している
- 代表は弁護士かつ弁理士である
- 外国語での契約書作成にも対応している
- 海外ブランドのその後の日本展開にも対応している
カルチャー・エンターテイメント法務に特化している
伊藤海法律事務所は、カルチャーやエンターテイメント法務に特化しています。そのため、契約書の作成のみならず、ビジネスモデルのリーガルチェックやトラブル対応など、あらゆる場面におけるリーガルサポートが可能です。
業界内の用語や商慣習などを熟知しているため、机上の空論ではなく、実効性の高いアドバイスを強みとしています。
代表は弁護士かつ弁理士である
デザイン制作業務委託契約では、知的財産の処理が一つの大きなポイントといえます。伊藤海法律事務所の代表・伊藤は弁護士であるほか、知的財産の専門家である弁理士資格も有しています。そのため、知的財産権の保護や適切な処理についても有効なサポートが可能です。
外国語での契約書作成にも対応している
円安が進んでいるなどの事情もあり、海外デザイナーの日本進出が進んでいます。また、インターネットが非常に発達した昨今、国や地域を問わずビジネスが展開されることは、もはや珍しいことではありません。
このような背景もあり、外国語で契約書を作成すべき場面も今後さらに増えていくことでしょう。伊藤海法律事務所は、外国語での契約書作成にも対応しています。
海外ブランドのその後の日本展開にも対応している
海外のファッションブランドが、日本でビジネスを展開する場合があります。伊藤海法律事務所では、海外ブランドによる日本展開のアフターフォローにも対応しています。
まとめ
デザイン制作業務委託契約書の概要や設けるべき主な条項、デザイン制作業務委託契約書の作り方などを解説しました。
デザイン制作を外部委託する際は、デザイン制作業務委託契約書の締結は必須といえます。契約書がなければ、契約内容などに齟齬が生じてトラブルとなるおそれがあるほか、デザイナーが契約に関して問題を起こした場合であってもスムーズな解除ができず、対応に苦慮するおそれも生じるためです。
とはいえ、テンプレートを活用しても、契約実態に即したデザイン制作業務委託契約書を自社だけで作成するのは容易ではありません。そのため、デザイン制作業務委託契約書の作成は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
伊藤海法律事務所はカルチャー・エンターテイメント法務に注力しており、デザイン制作業務委託契約書の作成やレビューについても豊富な実績を有しています。デザイン制作業務委託契約書の作成でお困りの際は、伊藤海法律事務所までお気軽にご相談ください。